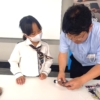Chip Camp in 奈良開催報告〈part1〉
2025年4月、ガールスカウト日本連盟はマイクロン財団の支援、広島大学の協力を受けて、女子のためのSTEAM教育*事業「Chip Camp in 奈良」を開催しました。
*STEAM教育:Science、Technology、Engineering、Art、Mathematicsを統合的に学習する、理数教育に創造性教育を加えた教育概念。
|
実施日|2025年4月1日-4月3日 |
5回目の開催となる今回は、14都府県から59人の中学生、高校1年生が参加しました。本ブログでは、3日間の豊富なプログラムの中から今回ならではの取り組みにハイライトし、3回に分けて報告します。
米マイクロン財団事務局長から、少女たちへのメッセージ

この活動をご支援くださっている「マイクロン財団」は、アメリカに本部を置いています。2024年末に就任されたRosita Najmi 事務局長は、ワシントンDCから、日本のSTEAM教育の視察に来てくださいました。参加者と対面し、こんなメッセージをいただきました。
みなさんこんにちは。Rositaです。ワシントンDCに住んでいます。
25年前、大阪に住んでいたことがあり、今日ここへ来るまで懐かしく思い出していました。出発の時には、2人の息子に、「これからお母さんははるばる奈良までSTEAM Programの視察に行くんだよ」と話しました。
みなさんが参加してくれて、とても嬉しく思います。みなさんの中には、初めて家族を離れて宿泊の経験をする人もいるかもしれません。ここまで長い道のりを経て来た人もいるかもしれません。この場に来るまでにたくさんのチャレンジがありました。
おめでとう!参加できたことを称えましょう!
マイクロンジャパンの同僚たち、仲間たちとも会えてとても嬉しく思います。みなさんそれぞれに異なるタイプのエンジニアです。私の仕事は、こうやってたくさんの人々と会い、未来ある若い人たちをサポートすることです。自分の仕事を自分にとってベストな仕事だと思っています。
マイクロンが何を作っているか知っていますか?
—参加者の回答|「メモリ」
そう!メモリです!メモリはどんなところに使われているでしょうか?
—参加者の回答|「スマートフォン」
そうです!スマートフォン。では、メモリは何でできているでしょうか?
—参加者の回答|「半導体。」
そうです。私たちは、半導体メモリを作っています。この後セッションで出てくるAIの分野にも大きく貢献しています。みなさんにぜひ学んでいただきたいと思います。
広島大学のみなさま、ガールスカウト日本連盟のみなさま、どうもありがとうございます。
これは本当に貴重な機会です。
プログラムを作ってくださって、セッションをおこなってくださる広島大学の先生方に心から感謝いたします。
みなさんは広島大学の先生、学生、ガールスカウトのリーダー、マイクロンのエンジニアから学ぶことができるんです。こんなことはなかなかありません。なので、たくさん手を挙げて質問してください。
私も今日は授業を見学します。楽しんで、学んでください!
英語でのスピーチは新鮮で、参加者たちは目を輝かせてメッセージをキャッチしていました。


アイデアソン『未来の学校』
広島大学 鈴木准教授によるセッションでは、学校生活から困っていることを発見し、よりよい生活を考えました。課題を解決するアイデアや、普段から思い描いていた自分の願いを叶えるアイデアを出し合いました。

10のグループがそれぞれ話し合い、テクノロジーを駆使したアイデアを発表しました。
初めて会う仲間とも、すぐに打ち解けて協力できるのがガールスカウト。
この時も、各グループで自然と進行役、記録役を分担し、普段の生活、学校生活の中にどんな困りごとがあるか、次々と課題が挙がりました。
少女たちはにぎやかに話し合いながら、ワクワクするアイデアを出し、発表をしました。どのグループも自分達のアイデアを発表したくてたまらない様子。
「私たちは、学校での教室移動が大変なので、教室が動いたらいいと考えました。」
鈴木准教授のコメント
「これはやりたいね。どちらが動くかが問題だね。教室が動くのか、廊下が動くのか。これは先生も以前に考えたことがある。歩道橋は、子どもを車から守るためにあるけれど、子どもにとっては歩道橋を渡るのがひと仕事になる。どうやって減らそうか? そこで、歩道橋じゃなくて、くぐらせる、アンダーパス、という発想があるんだよね。」
「授業中、眠くて困ることがあると思います。そこで、教室のカメラに体温とアプリをつけて、眠そうな人=体温が高くなっている人をカメラが発見するとイスを冷たくして、眠気を防止します。」
鈴木准教授のコメント
「すごいね。おもしろい。そんな机を使うことになったら便利そうだけど、監視社会、息苦しさもあるね。眠くなっている人がいるということは、眠くない授業をするべきだよね。これは、先生がおもしろい授業をしないといけない!」
「職員室に行っても先生に気づいてもらえないことがあるから、インターホンをつけて、先生の机の光で気づくようにします。」
鈴木准教授のコメント
「気づかない先生、いそがしいのかな。先生に声をかけるときに、自分の気分に合わせて色が出ると良いかもしれないね。」
どのアイデアも、今まさに企業や研究所で開発が進めていることであり、ものとものをネットワーキングする技術にとても近い内容だったと全体の印象を話してくださいました。さまざまな意見をまとめ、短時間で発表にいたる姿はガールスカウトならではのコミュニケーション力の高さと評価もしてくださいました。
学校教育では、高校生以上のカリキュラムで学ぶ「2進数の数の数え方」や、論理演算子のスキームを使った「人間計算機」のアクティビティも体験し、参加者たちはすっかりコンピュータの世界に入っていきました。
次へ続く